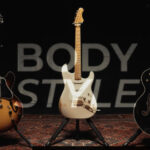僕が高収入の音楽の仕事を辞めた理由【音楽大学・専門学校の闇】
- 2025.04.10
- その他(ビジネス)
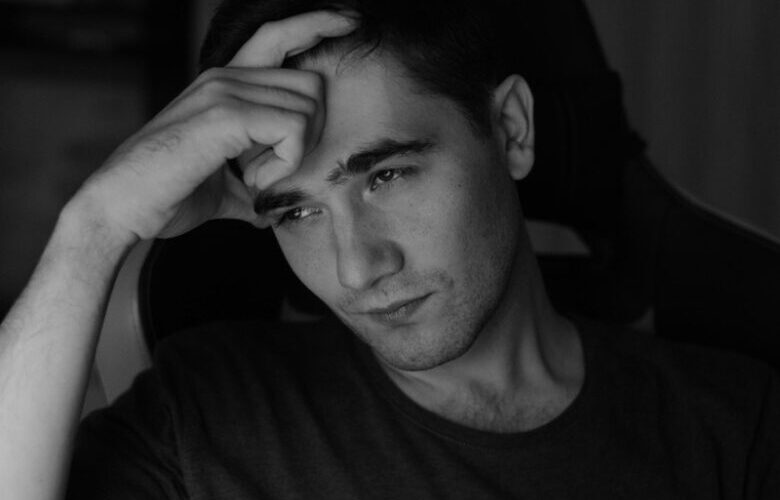
今回は、音楽プロデューサー・オーディオエンジニアのJustin Collettiが語る「僕が夢の仕事を辞めた理由」をまとめました。
この記事ではこのうち「Justinが音楽学校の重役を辞めた理由」の部分をまとめています。
Justinは長年音楽業界でプロとして活躍しており、音楽プロデュース、ミキシングエンジニア、マスタリングエンジニア、音楽大学の講師など、幅広い分野で活躍しています。
そんな彼は、2024年までにこれらの「夢の仕事」を辞め、新しいキャリアを歩み始めました。
ずっとやりたい仕事であったのに、高収入でもあったのに、彼はなぜ辞めてしまったのでしょうか?
スポンサードサーチ
はじめに:音楽プロデューサー&エンジニアのJustinの経歴

僕(Justin)は、長年夢見ていた仕事を自ら辞めました。
「SAE Institute」という素晴らしい音楽学校・教育機関の重役を辞め、有名音楽スタジオのミキシングエンジニアも辞めました。
そして、今の僕は前よりもとても幸せな人生を歩んでいます。
夢であった仕事を辞めたのは、とてもたくさんの収入を得られた仕事を辞めたのは、僕がその業界で「見たくなかったもの」を見てしまったからです。
音楽教育や音楽テクノロジーの世界では、僕が起こってほしくないと思うようなことが起こっていたのです。
・11~12歳で作曲をはじめ、22歳からプロとしてのキャリアをスタート
・芸術系の大学(Purchase University)を卒業
・ニューヨークの有名音楽スタジオのアシスタントとして勤務
・SAE Instituteのオーディオ部門の重役として勤務
・オーディオ&マスタリングエンジニアとして活動
それではここからは、僕がニューヨークの有名音楽学校の重役に抜擢されたものの、その仕事を辞めた話をご紹介します。
ニューヨークの有名音楽学校の重役に抜擢された話

僕はニューヨークで一番大きな音楽教育スクールである「SAE Institute」に勤めていましたが、「もっと低いコストでもっとよく教えられるはずだ」と思ったので、辞めました。
つまり、学生のためにならないような学校だと思ったので、この仕事を辞めたのです。
はじまりは2023年〜2024年ごろでした。

とある会社の人に「SAE Instituteという音楽学校のオーディオテクノロジー部門の重役にならないか?」と誘われました。
僕が投稿していた個人ブログを見て、僕を誘うことを決めたそうです。
なんと、その仕事では年間数十万ドルという多額の収入も提示されました。
※2025年時点、日本円で約1500万円以上
2000年代中盤は音楽制作で得られた収入が300~1000万円ぐらい、平均で700万円ぐらいでしたから、数十万ドル(約1500万円以上)という数字は僕にとってはとんでもない金額です。
もし年間数十万ドルを稼ごうとしたら、音楽制作以外にも仕事をしないと手が届きません。
しかし、その仕事ではたった1つの仕事だけで数十万ドル稼げたのです。
スポンサードサーチ
音楽学校での仕事内容は?

その会社が運営している音楽スクール「SAE Institute」は250名の生徒と22名の講師が在籍しており、うまく教育ができるようプログラム(カリキュラム)を作るという仕事内容でした。
それまで大学でレコーディングやミキシング、マスタリングを教えたこともありますし、教える仕事はとても好きでした。
YouTubeでも週1で音楽制作に関する動画をアップするほどです。
しかし、僕はこの学校で勤めることに不安を覚えていました。
確かに収入は魅力的でしたが、はじめの頃は「うーん、僕が一番やりたいことはではないかもしれない…」と思っていたのです。
ところが、この学校について知れば知るほど、この学校の魅力に気づくことになりました。
SAE Instituteはどんな音楽学校?

SAE Instituteは、1970年に創立された歴史のあるスクールです。
はじめはオーストラリアの小さな学校から始まりましたが、政府の補助金などを得ずに、今では世界に50校あると大きなスクールとなりました。
なぜこのスクールがここまで発展したかと言うと、音楽制作に関するさまざまな知識をしっかり学ぶことができ、その確かな技術のおかげで就職先も見つけやすく、学生・志望者から信頼されているからです。
確かな教育のおかげで学生から信頼を得ることができ、補助金などがなくてもしっかり経営ができるほどの力があったのです。
さらに学校内で奨学生制度もあったので、お金がなくても優秀な学生であれば入学することができ、優秀な生徒を獲得できるシステムも築いていました。
このスクールは大学や専門学校ではないので、卒業しても学位を得ることはできません。
9~18ヶ月のプログラムを終えると卒業できるスクールです。
しかし、短期間で音楽業界で必要な知識を教わることができるので、学位はなくても確かな技術が身につきます。
実際に、当時は就職率もよかったです
スポンサードサーチ
必要な知識を最短で学ぶことができる音楽教育機関だった

SAE Instituteは確かに素晴らしいスクールだとは思っていましたが、一方で少し疑い深くなってしまうこともありました。
もともと僕は大学で音楽を学びましたし、大学で音楽制作を教えた経験がありました。
そしてこの大学という場所は「学位も取れないような学校は果たしてちゃんとした学校なのか?」「大学ではなくただの専門学校なんて…」「修士号や博士号を取るために大学院に行った方がいい」「専門学校の教授になるよりも、大学の教授になった方がいい」というような考え方をする世界だったのです。
しかしSAE Instituteは専門学校で、たくさんお金を払って必要な技術を最短で学ぶことができる場所です。
学歴や権威などにとらわれず、必要な知識を最短で学ぶことができるなんて、こんなに素晴らしいことはないと思いました。
大学で音楽を教えていて、大学には行く必要はないと思った理由

そもそも昔は、作家やミュージシャンになるために大学に行っている人はいませんでした。
自分で見つけた・はじめた活動をすることでスキルを磨いていくのが主流だったからです。
しかし最近では変な文化が広がり、「20代ぐらいで音楽のプロになりたいなら音大に行った方がいい!」などの意見が見られるようになりました。
それにもかかわらず、4年間頑張って高い学費を払って大学で勉強しても就職先は見つかりません。
僕が教えていた大学では音楽に限らずアート、映画、ダンスなどを学ぶ学生もたくさんいましたが、どの分野でも4年間頑張って通った結果プロとしてお金を稼げる人はほんの数%しかいません。
そのため、まだ18歳ぐらいの人は高いお金を払って4年間費やして大学で音楽を学ぶ必要はないと思ったのです。
学生ローンや返済気必要な奨学金を借りて大学に通っても、最悪の場合は返済できずに破産してしまう人もいます。
加えて音楽業界で学位が必要になることはほとんどありませんので、そんなリスクを背負ってまで大学で音楽を学ぶ必要はないと思いました。
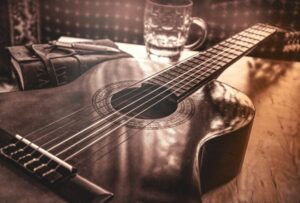
そのような考えもあり、学位が取れなくても9~18ヶ月間でプロとして必要なスキルを学べるSAE Instituteは本当に素晴らしいと思ったのです。
本当に音楽業界で働きたいなら、SAE Instituteのような学校に行くべきだと思いました。
そして、僕はSAW Instituteで働くことに決めたのです。
スポンサードサーチ
勤めていた音楽学校の教育方針が変わって絶望した話

僕がSAE Instituteに所属したときは、このスクールにとってちょうど転換期でした。
スクールがオーストラリアのNavitasという会社の子会社になった時期だったのです。
そして、この親会社の意向は「もっと信頼のある学校にするために、学位を取れるプログラム・学部を作るべきだ」というものでした。
「学位が取れる音大ブランド」は、志望者には魅力的に見えるでしょう。
学位を取れる学校であれば、政府からの補助金ももらえるので、もっと経営がしやすくなるというのも理由の1つだと思います。
しかしこの動きが始まってから、このスクールはどんどん悪くなっていきました。
「優秀な学生を集め、必要ならば奨学金を出し、スクール全体のレベルを上げて、素晴らしい人材を育て輩出していこう」という本来の方針が「いかに政府から補助金を得るか」「いかにたくさんの学生を集められるか」に変わってしまったのです。
学位が取れる音楽学校に待ち受けていた悲惨な現実

政府から認定された学校であれば、「学位が取れる学校」になることもでき、学生も学生ローンが組めるようになるので、今すぐ多額のお金が払えない学生も学校に通うことができます。
※アメリカの学生ローンのほとんどは、政府からの助成金を財源にしています
「学生ローンが組みやすくなれば、行きたい学校に行ける生徒が増える」「低所得者の人も、夢を諦めず行きたい学校に行けるようになる」というのはとても魅力的に聞こえます。
しかし、音楽大学をはじめとする音楽教育機関で実際に起こっているのは、こんなに魅力的なことではありませんでした。
学生ローン(返済が必要な奨学金)を得て入学した人が、多額の借金を抱え、学校のレベルも下がるケースが増えてしまったのです。
音楽学校に行っても意味がなくなってしまった原因とは?

もし成績が悪く落第するべき学生を落第させると、政府からの認可・保証や補助金を受けられなくなってしまいます。
「中退率・退学率の高い学校だ」「卒業率が悪すぎる」などと思われてしまったら、政府から信頼されなくなってしまうからです。
そのため、学生を増やすには学校のレベルを下げて入学しやすくし、成績が悪い人でも進級・卒業できるようにしなければいけなくなります。
これはSAE Instituteに限らずどの音楽学校でもそのようになっているのですが、「音楽の学位を取れますよ」「博士号も取れますよ」などと宣伝したいがために学校のレベルを下げることによって、本当に誰でも入学・卒業できるような学校になってしまっています。
つまり「大学に行って卒業する=確かなスキルを持っていること」の証明にはもうなっておらず、学位は何も意味をなさなくなってしまったのです。
もちろん、本当に熱心に勉強すれば、卒業するときには確かな技術が身に付いているでしょう。
しかし、そのような頑張り屋な学生であるか、何か特別な才能がない限り、学位だけで就職先が見つかる保証もなくなってしまいました。
悪化する学校側の体制に絶望し、退職した話

この学校の方針変更により「学位が取れる学校として政府に認定されるための要件を満たしているか」が重要視され、それをチェックするためのコンプライアンス担当の職員も新しく採用されました。
このコンプライアンス担当の職員は、学生たちが同意していることとは反対のことを行い、了承も得ないまま学校の方針を変えてしまうような人でした。
例えば、学位を取得するためにはある一定の授業内容と単位を取得しなければなりませんが、単位や卒業に関する制度が変わると在学生と新入生で差が出てしまいます。
これから入学する新入生は、卒業と学位取得に必要な単位数など、新しい制度の仕組みを理解して入学することができます。
しかし、在学生は入学時に聞いていた卒業要件や授業内容とは異なることが在学中に起きてしまいます。
そのため、このように制度を変えるときは新入生と在学生で卒業要件や授業内容を変え、在学生が不利になったり負担が重くならないように調整することが一般的です。
しかしそのコンプライアンス担当の職員は、在学生に許可を得ることなく新しい制度を強要したのです。

在学生にしてみれば、急に学校の方針を変えられて、やる必要ないと思っていた授業を卒業のために受けなければならず、大変な思いをします。
あまりにもひどいやり方でしたが、幸運にもその職員はやがてクビになりました。
僕は一安心したのですが、その数ヶ月後に学校の新しいCEOとディレクターが入社し、なんとクビにしたその職員をまた雇ったのです。
おそらく、その職員とCEOやディレクターはもともと仲がよかったのでしょう。
この職員をまた雇うような学校なら、僕はもうこの学校を辞めようと思いました。
そして、十分な引き継ぎを行った上で退職しました。
本当に、この学校のやり方には失望しました。
音楽学校に入学して後悔したときの話

ここで話を少し昔に戻して、僕が音楽大学に入学したときのことを話します。
2000年代は、アメリカで音楽制作(DTM)を勉強できる学校は5校ぐらいしかなかったと思います。
僕はSUNYという学校を受験しましたが、5人の応募に対して500人が応募しているほどの人気ぶりでした。
そのため、SUNYのように音楽を学べる学校に落ちてしまったときのことを考えるととても怖かったし、受験も本当に緊張しました。
当時の僕はオーディオエンジニアリングに関する本を3冊読んでいて、すべてを一気に理解しているわけではなかったのですが、それが功を奏したのか合格することができました。
しかし、学校では技術的なことで大きな学びになることはなく、持っている技術は基本的に独学で身につけました。
音楽学校に入学して犠牲になったものとは?

音楽学校でいい人脈は作れましたし、学費はそこまで高くなかったので借金を抱えて卒業することもありませんでした。
その点はよかったのですが、僕は大切なことを犠牲にしていたのです。
大学に入学する前、18歳の頃はお店でギターを売ってかなりの収入を得ていたのですが、大学の入学が決まったことでその収入のほとんどがなくなり、大学4年次のときにはやっていた仕事をすべて辞め、文字通り「ただの学生」になりました。
大学に行っている間は、自分で制作活動をしたり、レコーディング活動をしたり、音楽スタジオで働くことをせず、学校の勉強ばかりしていました。
つまり、大学に行くことで大金を費やして音楽を学ぼうとしたのであり、学びながらお金を稼ぐことはしなかったのです。
音楽学校に行ってこれを犠牲にしてしまったことは、とても後悔しています。
音楽学校に行くか迷っている人に考えてほしい「需要の法則」

この経験から、僕は音楽学校に行くべきかどうかを判断するための「とある法則」を見つけました。
もし人々があなたにお金を払ってでも知りたいと思っているなら、それは需要がある内容(スキル)である可能性が高い。
例えば2000年代前半は、今のように誰もがDTMや音楽制作をできるような時代ではありませんでした。
だから、音楽学校の試験で5人の枠に500人が応募するほど需要があったのです。
しかし、今では10代の学生も自分の部屋でDTMをするようになりました。
簡単な打ち込みやレコーディングの仕方なら、誰でもわかる時代です。
そのため、わざわざ高い学費を払って大学に行って音楽制作を学ばなくても、ある程度のことはYouTube動画を見るだけで間に合ってしまうのです。
またお金を払って学べることは、いずれ「みんな学んでいること」「みんな身につけているスキル」になるため、特別なスキルや知識でなくなる可能性が高いです。
ちなみに音大・専門学校の進学に関する記事はこちらにまとめていますので、進学で悩んでいる方はぜひ参考にしてください↓
今回のお話は以上です。
次回「夢だったミキシングエンジニアの仕事を辞めた話」はこちら↓
-
前の記事

初心者向け・正しいエレキギターの選び方【あなたに合うのはどのタイプ?】 2025.04.06
-
次の記事

僕が高年収の音楽の仕事を辞めた理由【NY有名スタジオを辞めた話】 2025.04.10