今回は、SonicScoopが解説する「大きいスピーカー vs 小さいスピーカー ~大きいスピーカーを買えばいいミックスができるのか?~」をまとめました。
プロの音楽家のスタジオを見ると、高価で最高音質のスピーカーがありますが、それらはどれも非常に大きいです。
一般家庭の部屋に置くには大きすぎるサイズのものもありますが、プロになるのであれば大きいスピーカーを買わなければならないのでしょうか?
言い換えれば、大きいスピーカーを買えば、いいミックスやマスタリングができるようになるのでしょうか?
それとも、小さいスピーカーでも十分「いいミックス・マスタリング」はできるのでしょうか?
こちらを詳しく解説していきます。
結論:大きいスピーカーを買った方がいいミックスができるのか?
結論から言うと、これは「半分YES」で「半分NO」です。
「大きいかどうか」ではなく、「自分に合ったスピーカーであるかどうか」が重要になります。
ここからは、この具体的な理由やさまざまなシチュエーション、おすすめのスピーカーなどについてご紹介していきます。
スピーカーの質に関する3つのチェックポイント
まずはじめに、スピーカーを選ぶときの3つのチェックポイントを確認しましょう。
おそらく、多くの方が以下3つについて考えながらスピーカーを選んでいると思います。
3つのチェックポイント
- 値段
- サイズ
- パフォーマンス
これらの3つの観点から、実際の音質とどのように関係しているのか、大きいスピーカーの方がいいのか、それとも小さいスピーカーでも問題ないのかを解説していきます。
「大きくて安いスピーカー」はおすすめ?

例えば「ADAM T8V」は8インチのスピーカーで、お値段はペアで7万円程度、一般家庭の机に置くのはやや大きめ・重めのスピーカーです。
8インチという大きめのスピーカーの中にしては、かなりリーズナブルな価格帯です。
値段はリーズナブルですが、しっかり低音域も出ますので、「サイズは大きくてもいいけれど値段は抑えたい」という方にはおすすめです。
「小さいのに値段が高いスピーカー」はおすすめ?

対して、先ほどの「T8V」よりも少し小さい「ADAM A4V」は、4インチ+ペアで10万円程度です。
先ほどのT8Vよりも4インチ小さいのに、値段が高いのです。
基本的に、「値段が高ければ高いほど、いい音質だ」と思われがちです。
これは、内部にいい音を鳴らすためのいいドライバーが備わっている=値段が高いという理屈です。
これにプラス、よりよいデザインや理想のサイズ感なども求めていくと、自然にコストが上がっていきますので、結果的に値段が高くなる、というわけです。
現代の技術的に「小さいのに音質がいい」を達成するのは難しいので、「小さいのに高いスピーカー」が存在するのです。
「小さいのに音質がよく高価なスピーカー」の特徴
小さいのに音質がよく高価なスピーカーの特徴は、主に3つあります。

1.フリークエンシーレスポンスがいい
周波数帯域に関わらずバランスよく鳴らせるか
2.トランジェントレスポンスがいい
トランジェント(音の立ち上がり、アタック)をキレイに鳴らせるか
3.中音域が精密
これら3つの特徴から、「小さいけど音質がいい」を実現できています。
これにプラス「机に置きやすい」など、物理的に置けるかどうかの問題にも対処できるのがメリットです。
そのため、「できるだけ小さいスピーカーがいいけど、音質はいいものが欲しい」という人は、このような「高価だけど小さいスピーカー」を選ぶとよいでしょう。
小さいスピーカーとサブウーファーの組み合わせもおすすめ
高価で小さいスピーカーでも、やはり大きいスピーカーのように「1つで超低音域から高音域までを完璧にカバーできる」というわけではありません。
高価で小さいスピーカーは、確かにサイズにしては低音域もしっかり出ますが、やはり「高価で大きいスピーカー」には敵わない部分があります。
それが低音域です(特に40Hz以下)。
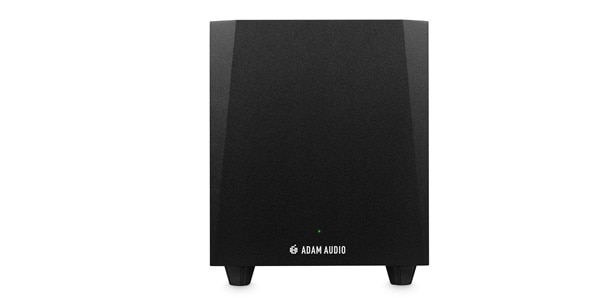
そのため「高価で小さいスピーカー」を買った場合は、追加でサブウーファーを買うという手段もおすすめです。
こうすれば、少なくとも中音域以上は「高価で小さいスピーカー」でしっかりカバーし、低音域はサブウーファーでカバーできますので、低音域から高音域までしっかりモニタリングすることができます。
言い換えると、高価で小さいスピーカーは2wayスピーカー(高音域と中音域)を専門とし、サブウーファーは1wayスピーカー(低音域)を専門としていますので、両方使うと「3wayスピーカー」を使っていることになります。

ちなみに上記画像のように高価で大きいスピーカーは、これらを1つのスピーカーにまとめているので「3wayスピーカー」と呼ばれています。
「高価で大きいスピーカー」はおすすめ?

大きいスピーカーは、大き過ぎて机に置けなかったり、スピーカースタンドが必要になる場合があります。
モニタリングの位置を考えると、自分とスピーカーの間にはある程度の距離も必要になりますので、小さい部屋でのモニタリングにはあまり向いていません。
部屋がある程度広い場合は、スピーカーと適切な距離を置けますので、部屋の大きさにゆとりがある場合は大きいスピーカーを選んでも問題ないでしょう。
適切な位置にスピーカーを置くための「4倍ルール」
同じ位置でも、大きいスピーカーを置けば自分とスピーカーの距離が縮まり、小さいスピーカーを置けば自分とスピーカーの距離は遠くなります。
しかし、スピーカーを置く位置を適切にしないと、スピーカーが本来持つパフォーマンスを最大限発揮できずに終わってしまいます。
これを解決するのが「4倍ルール」です。
スピーカーと自分の間の距離は、「スピーカーのサイズを4倍にした距離」にしましょう。
例えば4インチスピーカーであれば、4インチ(約10cm)x 4 = 16インチ(約40cm)となりますので、自分とスピーカーの距離が40cm離れた場所に置くのがよいでしょう。
8インチスピーカーであれば、8インチ(約20cm)x 4 = 32インチ(約80cm)となりますので、自分とスピーカーの距離が80cm離れた場所に置くのがよいでしょう。
(部屋を音楽制作用に特別に設計していない限りは、おおよそこの値が理想です)
低音域やサブウーファーを台無しにしないためには吸音材がおすすめ
実は、サブウーファーなどを使って低音域を適切に聞く方法には注意点があります。
一般家庭のごく普通の小さい部屋でスピーカーを使うと、低音域が響き過ぎて低音を適切にモニタリングすることが難しくなります。
つまり、どんなにいいサブウーファーを使っていたとしても、部屋そのものが適切に設計されていなければ、そのサブウーファーも台無しになってしまいます。
そのため、もしご家庭の一般的な小さい部屋で音楽制作をしている場合は、吸音材などを使って低音域が響き過ぎないように調整しておくことが重要です。
音楽制作用のスタジオとして設計していない限り、一般家庭の部屋は音の反響について考慮されて設計されているわけではありませんので、自分で吸音材などを使って反響をコントロールすることが大切です。
これを考えずに放置しておくと、特に200Hz以下の低音にかなり影響が出ますので、こちらはぜひ気をつけましょう。
どんなにいいスピーカーを使っていても台無しになってしまう例
これまでの解説を踏まえると、どんなに高価なスピーカーを使っていても、しっかり自分の環境に合っているスピーカーを選ばなければ、そのスピーカーが持つ力を最大限発揮できないことがわかります。
スピーカーを置く部屋の大きさや、しっかり吸音材などで反響をコントロールできているかなどが重要になります。
そのため、「大きい・小さい」「高い・安い」だけではなく、これらの要素にも気を配る必要があります。
「ニアフィールドモニター」と「ミッドフィールドモニター」の違いとは?
ここで、「ニアフィールドモニター」と「ミッドフィールドモニター」の違いのお話をしましょう。
ニアフィールドモニター
1人の人が、適切な場所でスピーカーからの音を聞いているところを想定して作られたスピーカー
ミッドフィールドモニター
音楽スタジオのような、比較的大きな部屋で音を聞くところを想定して作られたスピーカー。
複数人の人にとって「スウィートスポット(ベストポジション)」が得られるように作られている。

ミッドフィールドモニターは、例えば下の画像の「ADAM A77H」のように比較的大きく、座っているイスから少し離れたところに置かれていることが多いです。

「自宅の小さな部屋でDTMをしている」という場合はニアフィールドモニターで、「音楽スタジオを経営している」「広い部屋に置くためのスピーカーが欲しい」という場合は、ミッドフィールドモニターを使うとよいでしょう。
スピーカーのドライバーのサイズにも注意
例えばミッドフィールドスピーカーの「ADAM A44H」は、4インチドライバーのスピーカーです。

ドライバーが少し小さめで値段もリーズナブルなので、この場合は低音域までしっかりモニタリングするためにも、サブウーファーを追加するのがおすすめです。
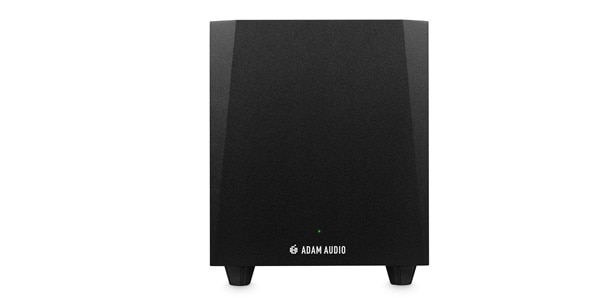
このようなサブウーファーも追加すれば、ニアフィールドモニターのよりも非常によくモニタリングできるようになります。
ちょうどいい大きさのスピーカーの例
こちらの「ADAM A7V」というスピーカーは、一般家庭の机に置くには少々大きいスピーカーでずっしり重く、お値段はペアで20万円程度、7インチのスピーカーです。

この程度の大きさのスピーカーでは、40Hz台の低い音もしっかり聞くことができ、プロも愛用している人が多いタイプです。
もちろん、これより大きいスピーカーもありますし、これより小さいタイプのスピーカーもありますが、コスパで選ぶのであればこれぐらいのスピーカーがおすすめです。
特に、この「ADAM A7V」は低音から高音までしっかりバランスよく聞こえるようになっていますので、音楽制作を本格的にしたい方におすすめのスピーカーです。
大きいスピーカーを買った方がいいミックスができるのか?まとめ
今回は「大きいスピーカーを買った方がいいのか?」について解説しました。
ポイント
・必ずしも大きければいいというわけではない
・自分のシチュエーションに合ったスピーカーを選ぶのがベスト
・吸音材や部屋のサイズなどの”環境”づくりも重要
・ドライバーが小さい場合はサブウーファーも一緒に使うのがおすすめ
当サイトでは、他にもスピーカー・イヤホン・ヘッドホンやミックスに関する記事をご紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください↓


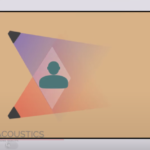


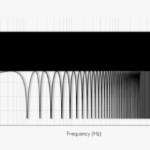



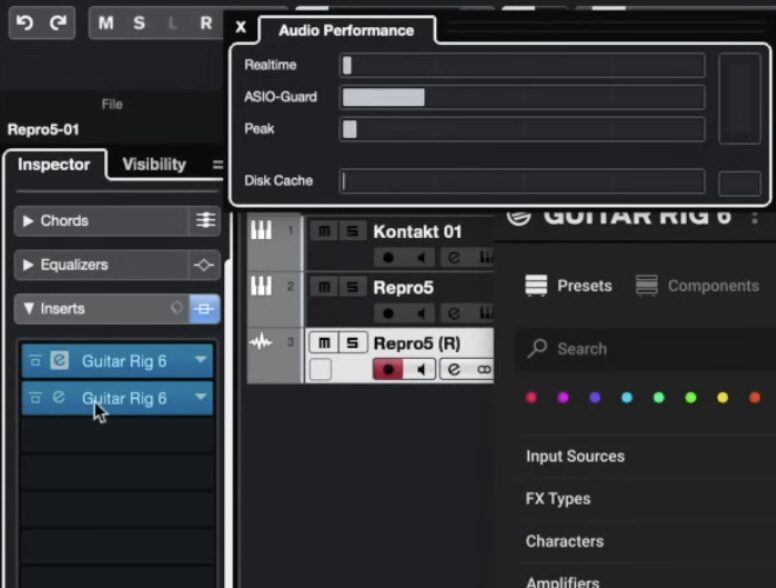






.jpg)